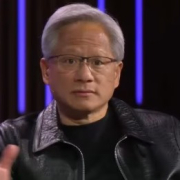NVIDIA CEO Jensen Huangが「米AI規制がHuaweiを利する」と警鐘
2025年5月7日
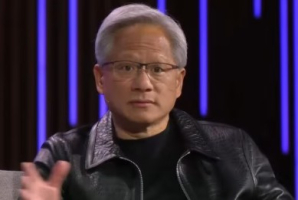
米半導体大手NVIDIAのCEOであるJensen Huang氏が、米国のAI半導体輸出規制に対し「逆に中国の競合企業、特にHuaweiを利する可能性がある」と強い懸念を表明した。この発言は、AI技術の覇権を巡る米中対立の複雑な実情と、今後の米国のAI戦略のあり方に一石を投じるものとして注目される。
「我々は岐路に立たされている。米国がAIの世界的な開発と展開をリードし続けるのか、それとも撤退し守勢に回るのか決めなければならない」。NVIDIAのJensen Huang CEOは、米下院外交委員会での発言で、米国の現行のAI関連輸出規制に対して強い危機感を示した。
Huang CEOは、「米国が減速すれば、他者がその隙を埋めるだろう。そして世界のAIエコシステムは技術的、経済的、イデオロギー的に分断される」と指摘。特に、米国のプラットフォームが存在感を失えば、企業はHuaweiのような戦略的競合他社に目を向けることになると警告している。
彼の主張の核心は、「AIにおけるリーダーシップは、何を制限するかだけでなく、何を可能にするかにかかっている」という点である。NVIDIAが持つ600万人の開発者ネットワークという強力なエコシステムを失えば、それを取り戻すことはほぼ不可能だとし、「AI Diffusion Rule(AI拡散ルール)」が大幅な変更なしに施行されれば、NVIDIAは世界の他の地域からも同様に撤退を余儀なくされるとまで述べている。これは、単なる一企業の懸念を超え、米国のAI戦略そのものへの痛烈な問いかけと言えるだろう。
Huang CEOが名指しで懸念を示した「AI Diffusion Rule」とは、一体どのようなものなのか。このルールは2025年5月15日に発効するとされている物で、前Biden政権下で発表された物だが、その骨子は、高性能AIチップ(NVIDIAのH100などが代表例)へのアクセスを国ごとに階層化するというものだ。
- Tier 1(第一階層): 米国および選ばれた18の同盟国。これらの国々の企業は、高性能AIチップへ無制限にアクセス可能。
- Tier 2(第二階層): これらの国々の企業は、年間約50,000基のH100クラスGPUに制限される(特例承認や少量輸入枠を除く)。
- Tier 3(第三階層): 中国、ロシア、マカオなどが含まれ、武器禁輸措置により事実上、高性能AIチップの入手がブロックされる。
このルールの狙いは、米国の先端技術が敵対国に渡ることを防ぎ、安全保障上の優位性を維持することにあると考えられる。しかし、NVIDIAのようなグローバル企業にとっては、巨大市場である中国からの締め出しだけでなく、Tier 2諸国におけるビジネス展開にも大きな制約がかかることを意味する。Trump政権下では、この階層システムの見直しや、Tier 2諸国への制限強化も噂されており、規制の不透明感が企業活動の足かせとなっている側面は否めない。
NVIDIAの強みは、単に高性能なGPUを製造していることだけではない。Huang CEOが繰り返し強調するように、その核心には「CUDA」と呼ばれる並列コンピューティングプラットフォームと、それを取り巻く広大な開発者エコシステムが存在する。
CUDAは、AIの学習や推論処理において、NVIDIA製GPUの性能を最大限に引き出すためのソフトウェア開発環境である。現在、世界のAI開発のデファクトスタンダードとなっており、学術研究から産業応用に至るまで、幅広い分野で利用されている。Huang CEOが誇る「600万人の開発者」は、このCUDAプラットフォーム上で日々新たなAIアプリケーションを生み出しており、これがNVIDIAの競争力の源泉となっている。
規制によってNVIDIA製品の入手が困難になれば、開発者は他のプラットフォームへの移行を検討せざるを得ない。Huang CEOは、「一度誰かが特定の技術やプラットフォームに投資してしまうと、乗り換えは非常に高価で困難になる」と、かつての通信業界におけるHuaweiの事例を引き合いに出して警告している。エコシステムを失うことは、単に市場シェアを失うだけでなく、AI技術の進化の方向性を決める力を失うことを意味するのである。これは、Intelがx86やPCIe、USBで築き上げた標準化戦略の重要性を彷彿とさせる。
Huang CEOが名指しで警戒するHuaweiは、米国の規制強化をむしろ好機と捉え、独自のAIエコシステム構築を加速させている。
ハードウェア面では、Ascend AIプロセッサや、NVIDIAのGB200 NVL72ラック規模マシンを性能で上回ると主張する「Cloud Matrix 384」システムなどを開発。そしてソフトウェア面では、「CANN(Compute Architecture for Neural Networks)」という独自のAI指向ヘテロジニアス・コンピューティング・アーキテクチャを推進している。
CANNは、NVIDIAのCUDAと同様に、ランタイムシステム、モデル構築ツール、コンパイラなどを含む包括的な開発スイートを提供し、Huawei独自のMindSporeプラットフォームだけでなく、TensorFlowやPyTorchといった広く使われているAIライブラリもサポートしている。
確かに、CANNは現在、「パフォーマンスの不安定さ、ドキュメントの不備、信頼性の問題」といった課題を抱えており、CUDAからCANNへのプログラム移植には「数ヶ月と数百人の開発者」が必要とも言われている。しかし、Huaweiはこれらの問題を認識し、積極的に改善に取り組んでいるとされている。
重要なのは、中国国内市場という巨大な「実験場」と、政府からの強力な後押しがあることである。Huaweiは年間数百億ドルを研究開発に投じており、国内でAIハードウェアの販売を拡大できれば、エコシステムへの投資をさらに強化できる。これは、Biren Technology(創業者は元NVIDIA中国事業責任者のZhang Jianzhong)、InnoSilicon、Moore Threadsといった他の中国AI半導体企業にとっても同様の追い風となるだろう。これらの企業は、英国Imagination TechnologiesのPowerVR GPU IPを利用するなど、GPU開発の経験も豊富である。Biren Technologyの創業者Li Bingや共同CEOのAllen Lee(Li Xinrong、元AMD中国R&Dセンター幹部)のような人材が、中国のAI半導体開発を牽引している。
Tom’s Hardwareは、過去の5GインフラにおけるHuaweiの台頭を「警告的な事例」として挙げている。当時、Huaweiは安価で迅速に導入可能な5G機器を提供することで、世界の多くの市場で大きなシェアを獲得した。これにより、技術標準における影響力を高め、米国の安全保障上の懸念を引き起こした経緯がある。
AI分野でも同様のことが起こりうる、というのがHuang CEOの警告の根底にあるのだろう。もし中国企業が、特に中国国内や「一帯一路」構想に関わる国々で独自のAI技術標準を確立してしまえば、世界のAI市場は分断され、米国企業の活動領域は狭まる。それは単にNVIDIAの収益減に留まらず、AIのガバナンスモデルや倫理基準といった、より広範な分野における米国の影響力低下を意味しかねない。
Huang CEOの警告は、一企業の利益擁護という側面を完全に否定することはできない。しかし、彼の指摘する「制限だけではリーダーシップは維持できない」「エコシステムの重要性」という論点は、テクノロジー業界の現実を的確に捉えていると言えるだろう。
米国の政策決定者は、国家安全保障上の懸念から中国への先端技術流出を阻止したいという強い動機を持っている。これは当然の配慮であり、軽視することはできない。しかし、その手法が過度に保護主義的になり、自国企業の国際競争力やイノベーションの芽を摘んでしまう結果を招いては本末転倒である。
AIのような急速に進化する分野では、オープンな競争とグローバルな協力がイノベーションを加速させる。DeepSeekのオープンソースR1モデルのような事例は、米国の技術リーダーシップの有無にかかわらず、イノベーションが世界中で急速に進んでいることを示している。米国企業が市場から締め出されれば、その空白を埋めるのは間違いなく競合他社であり、その中には中国企業が含まれるのである。
問題は、短期的な「封じ込め」と、長期的な「競争力強化」のどちらに力点を置くかという戦略的判断である。Huang CEOは、米国の技術とAIモデルを世界に広めることが、米国の利益、雇用、インフラを米国にもたらすと主張する。これは、自社の技術を積極的に世界展開することでデファクトスタンダードを築き、結果として米国のリーダーシップを確固たるものにするという、攻めの戦略と言えるだろう。NVIDIAはアリゾナにあるTSMCの工場で次世代Blackwellチップを生産し、FoxconnやWistronと提携して新たなAIインフラ工場を建設するなど、米国内での投資も進めている。
NVIDIAのJensen Huang CEOが投じた一石は、米国のAI戦略が極めて難しい舵取りを迫られていることを浮き彫りにした。「米国のAIリーダーシップのために何が必要か」という彼の問いは、単に半導体規制の是非を超え、イノベーションの本質、グローバル競争のあり方、そして未来のテクノロジー社会の姿をどう描くかという、より根源的な議論を私たちに促している。
Huang CEOは、「AIは単なるチップではない。それは完全なシステムだ。コンピューティング、ネットワーキング、ソフトウェア、エネルギー、そしてそれを推進する人々。だからこそ我々はAI工場について語るのだ。それは比喩ではなく、次世代経済の現実のインフラとして」と述べている。この言葉は、AIが社会基盤となる時代において、その基盤構築の主導権をどこが握るのかという競争が既に始まっていることを示唆している。
米国の規制当局が、Huang CEOの警告にどこまで耳を傾けるのか。そして、安全保障とイノベーション促進という二つの命題をいかに両立させていくのか。その判断が、今後の世界のAI勢力図を大きく左右することは間違いない。私たちもまた、この複雑な問題について、安易な結論に飛びつくのではなく、多角的な視点から探求を続ける必要があるのではないだろうか。